
| 2017年10月 もくじ |
| 飲む所作がさすが文蔵「試し酒」 菊まつり土曜にゃ笠間で落語かな 秋雨(あめ)の日にアイディアなどを二つ三つ 愛犬や昔の写真で出ています 国難突破と秋喧(かまびす)し選挙カー 突然の訃報哀しや秋の風 |
 |
| 続けて落語の話になりますが、28日の土曜日、「かさま落語会」での開口一番、お陰さまで無事つとめることが出来ました。 出演は、橘家文蔵師匠と、動物ものまねの、江戸家まねき猫さん。文蔵師匠は、泥棒より数枚上手なお妾さんの噺「転宅」と、大酒のみの下男の久蔵の噺「試し酒」。去年の9月に橘家文左衛門から三代目橘家文蔵を襲名し、ますます芸に磨きがかかって来ており、お客さまを魅了しておりました。  そして、江戸家まねき猫さんの動物ものまねも、お父さんの三代目江戸家猫八の洒脱さを受け継ぎ、小ざっぱりとした江戸前の芸で大いに受けておりました。 打ち上げでのスナップは、高田文夫氏、まねき猫さん、世話役の歯科医の綱川先生と私。喜樂家樂喜の「蔵前駕籠」も、手前味噌ですが、なかなかに好評でございました。 試し酒 ある大家の主人。客の近江屋と酒のみ談義となる。お供で来た下男久蔵が大酒のみで、一度に五升はのむと聞いて、とても信じられないと言い争い。挙げ句に賭けをすることになる。もし久造が五升のめなかったら近江屋のだんなが二、三日どこかに招待してごちそうすると取り決めた。 久蔵は渋っていたが、のめなければだんなの面目が丸つぶれの上、散財しなければならないと聞き「ちょっくら待ってもらいてえ。 さては逃げたかと、賭けが近江屋の負けになりそうになった時、やっと戻ってきた久蔵「ちょうだいすますべえ」一升入りの盃で五杯、息もつかさずあおってしまった。 相手のだんな、すっかり感服して小遣いをやったが、しゃくなので「おまえにちょっと聞きたいことがあるが、さっき考えてくると言って表へ出たのは、あれは酔わないまじないをしに行ったんだろう。それを教えとくれよ」「いやあ、なんでもねえだよ。おらァ五升なんて酒ェのんだことがねえだから、心配でなんねえで、表の酒屋へ行って、試しに五升のんできただ」 ネタ元は英国?中国? このときの速記者が今村の父・次郎ということもあり、今村はこのブラックの速記を日本風に改作。では、オリジナルはブラックの作または英国産の笑話かというと、それも怪しいらしく、さらにさかのぼって、中国(おそらく唐代)の笑話に同パターンのものがあるともいわれているとか。具体的な文献ははっきりしないということで、案外、世界中に類話は分布しているかもしれないということです。 初演は七代目可楽で、その可楽の演出を戦後、五代目柳家小さんが継承、ほぼ古典落語化するほどの人気作にしたということです。 |
 |
|
台風の中、衆議院選挙の投開票も終わり、自民、公明で定数の「3分の2」超313議席を獲得し、立件民主党が躍進し、小池ゆりこの希望の党は惨敗。東京は台風一過、1日置いて遊歩道やエントランスの落葉などを掃除し、やっといつもの平静を取り戻しました。 台風の22日は、選挙の開票結果の特番を観たり、ミドル級の世界戦、村田諒太とアッサン・エンダムの試合を観たり。台風の水漏れに慌てたり。床に付いたのは午前2時頃でした。 テレビでは、笠間神社で行われている菊まつりのニュースなども流れ、私が開口一番を務める「かさま落語会」もいよいよ今週末の土曜日28日に迫って来ましたので、毎日稽古をしています。演目は、前にも書きましたが「蔵前駕籠」です。噺の内容は… 徳川三百年、泰平の御代が終いに近づくと、神田・日本橋方面と吉原を結ぶ蔵前通りに、夜な夜な追剥が出没した。 「我々は徳川家にお味方する浪士の一隊。軍用金に事欠いておる、命が惜しくば、身ぐるみ脱いで置いてゆけ」と身ぐるみを脱がすと「武士の情け。襦袢だけは許してやる」「へえ、ありがとうございます」てな具合。 そんなわけで、茅町の江戸勘のような名のある駕籠屋は、評判にかかわるので暮れ六ツの鐘を合図に吉原行の駕籠を出さなくなった。 と、遊び人のだんな。吉原の花魁(おいらん)から、ぜひ今夜来てほしいとの手紙を受け取ったため、意地ずくでも行かねばならない。そこで、渋る駕籠屋に掛け合って、駕籠賃は倍増し、追いはぎが出たらおっぽり出してその場で逃げてくれていい、と、酒手は一人一分ずつという条件もつけてようやく承知させる。 そして、こっちも支度があるからと、何を思ったかそのだんな、くるくると褌(ふんどし)一つを残して着物を全部脱いでしまった。それをたたむと、煙草入れや紙入れを間に突っ込み、駕籠の座ぶとんの下に敷いてどっかと座り、「さあ、やれ」 駕籠屋が「だんな、これから風ェ切って行きますから冷えますよ」とからかうと、「向こうに着きゃ暖め手が待ってる」と変なノロケを言いながら、いよいよ問題の蔵前通りに差しかかる。 天王橋を渡り、前方に空地を臨むと、何やら怪しい影。「だんな、もう出やがった。お約束ですから、駕籠をおっぽりますよっ」と言い終わるか終わらないかのうちに、ばらばらっと取り囲む十四、五人の黒覆面の浪士たち。 駕籠屋は雲を霞みと逃げちまう。ぎらりと氷の刃を抜くと、「我々は徳川家にお味方する浪士の一隊。軍用金に事欠いておる、身ぐるみ脱いで置いていけ。命が惜しくば……これ、中におるのは武家か町人か」刀の切っ先で駕籠の御簾(みす)をぐいと上げると、褌一本の男が腕組み。「うーん、もう済んだか」 お陰さまで、順調に仕上がっています。 |
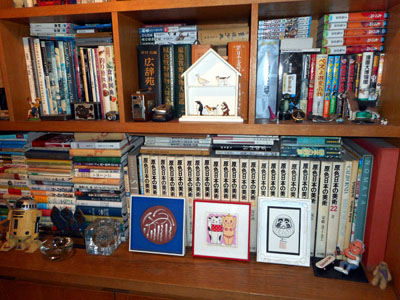 |
|
ここ何日か、雨が続いています。そんな日々、ギャラリー工のネットショップの企画を考えています。販売するものは、アート作品、アンティーク、手づくり雑貨などが中心。3人であれこれ考え、どうやら一つの方向にまとまりました。11月の中頃までには、オープンすることも話し合いました。勿論、このショップの名前も決まりました。 コンセプトは、「和と洋」、「新と旧」、「ハレとケ」、「手仕事&手づくり感」、「季節感」を大切にした品揃えということに。そこで、今、品もの選びと、サイト創りに取り掛かりはじめたのですが、更に、「今の時代感」、「身の丈感」、「ちょっとしたオシャレ感」、こうした気分も、品揃えやサイトに、行き渡ればいいなと思っています。 ところで、「身の丈にあった暮らしって何だろう?」と考えました。すると、無理のない暮らし。でも、時にはちょっと贅沢する暮らし。そして、日々が楽しい暮らし。そんな言葉が思い浮かんで来ました。 それでは、こうした暮らしにフィットするようなキーワードには、どんなものがあるかなと雑誌やネットを見ながら考えていたら、こんな言葉たちが出てきました。 「痒いところに手が届く」 などなど。さて、どんなネットショップになりますことやら。乞う、 |
 |
| まるで美空ひばりを聴いているようなCoCoのこの写真、パソコンの写真ファイルの中から探してひと笑いしました。
ところで、ひばりさんと言えば歌謡界の女王。その美空ひばりのカラオケで歌われる人気曲ランキングを調べてみましたら、次のようでありました。
1 愛燦燦 2 みだれ髪 3
川の流れのように 4 真赤な太陽 さて、私の好きなひばりさんの歌といったら、「越後獅子の唄」「お祭りマンボ」「花笠道中」「江戸の闇太郎」「関東春雨傘」そして、「さくらの唄」となります。 後獅子の唄 笛にうかれて 逆立ちすれば お祭りマンボ 私のとなりのおじさんは 花笠道中 これこれ 石の地蔵さん 江戸の闇太郎 月に一声 ちょいとほととぎす
関東春雨傘 関東一円 雨降るときは さくらの唄
何もかも僕は なくしたの この「さくらの唄」の関しては、久世光彦さんの名エッセイ「マイラストソング」で、こんな風に書かれています。 −略−昔、なかにし礼という不良がいた。不良には不良の辛(つら)さがあって、辛くてしょうがないので歌を書いた。−略−こっそり咳き込んで、ふと掌(て)を見たら、そこに色の薄い血が散っている―そんな歌だった。だからいま口にしてみても、言葉の一つ一つが、掌に掬(すく)った夕暮れの砂金のように優しく光っている。 −略−おなじころ、三木たかしという、これも不良がいた。食べられないので毎晩ギターを抱えて縄のれんを流して歩き、−略−塵芥(ごみ)の臭いのする路地裏の部屋にうずくまって呻(うめ)いていた。辛くてたまらないので歌をつくった。自分では言葉がつくれないので、なかにし礼の「さくらの唄」を貰った。気持ちがわかりすぎて、歌いながら涙がこぼれた。−略−歌手が誰も歌ってくれないから、自分で歌ってレコードを出した。一枚も売れなかった。 これで皆んないいんだ 悲しみも −略−売れなかった歌というのは、眠っているというよりは、死んでいるということだ。−略−しかし、この「さくらの唄」だけは、どうにかして蘇らせることができないものだろうか。―ドラマの中で流してみよう、と私は思った。 −略−それなら美空ひばりしかいない。私は自信を持って彼女の所属するコロムビアに交渉に行った。しかし、あっさり断られた。アルバムならともかく、一度他の歌手が歌った曲は、美空ひばりはシングル・カットしないというのである。女王の矜持(きょうじ)である。−略−レコード会社の言い分はもっともだったが、私は粘った。なんとか聴いてだけでも貰えまいか。それほどまで言うのなら、自分で行って頼んでごらんなさい。 私は大きなテープ・レコーダーを抱えて新幹線に乗り、名古屋で公演中の美空ひばりを訪ねた。−略−「もう一度聴かせてください」 −略−安っぽい人情噺と言われてもいい。私はこの夜のことを一生忘れないだろう。ひばりはポロポロ涙をこぼして歌っていたのである。そしてテープが終わると、私に向かって坐り直し、「歌わせていただきます」と嗄(しゃが)れた声で言って、それから天女のようにきれいに微笑った。 −略−美空ひばりの「さくらの唄」は、同じタイトルのドラマの主題歌として、半年の間、毎週テレビから流れ、同時にレコードとして全国で発売されたが、ほとんど売れなかった。−略−言い訳めくが、あまり良すぎても、レコードというものは売れないのである。けれど、いつ、どんなときに聴いても泣いてしまうという歌は、そうあるものではない。−略−一度でいいから聴いてみて欲しい。少なくとも私一人は、あの歌が美空ひばりの<ラスト・ソング>だと信じているのだから―。 私は、この久世さんのエッセイが大好きなのであります。 |
 |
| 10日、衆議院議員選挙の公示があり、いよいよ選挙戦に突入しました。それにしても、世の中、暢気に暮らそうと思っても、やはりなかなかそういう訳には行かないようで、身の回りは日々大変なことだらけ。惜しくも早世した知人がいたり、わが身を思えば、毎週木曜、抗がん剤治療でのがん研通いがあったり。なかなか長閑な気持ちになれません。
ところで、今回の選挙、結末はどうなることでしょう。朝日新聞の序盤の情勢調査では、自民堅調、希望伸びず、立件に勢いとありました。私の選挙区は東京8区。小選挙区は誰に入れるか、比例区はどの党に入れるか、粗方もう決めてしまったので、これからは、選挙戦を戦国の陣取り合戦や、幕末の討幕運動を見る気分で注目したいと思っているのですが、序盤でもう早くも勝負があったのでしょうか。細川護熙さんは、今回の選挙、討幕が応仁の乱になってしまったと冷たく言い放っていますが…。 森友、加計、憲法、増税、少子・高齢化、原発、北朝鮮… そこで、幕末の志士、長州藩士、高杉晋作の名言を味わってみる気になりました。なかなか含蓄に富んでいる言葉ばかりです。 「人間、窮地におちいるのはよい。意外な方角に活路が見出せるからだ。しかし、死地におちいれば、それでおしまいだ。だから、おれは困ったの一言は吐かない」 「戦いは一日早ければ一日の利益がある。まず飛びだすことだ。思案はそれからでいい」 「負けて退く人をよわしと思うなよ。知恵の力の強きゆえなり」 「人は人 吾は吾なり 山の奥に 棲みてこそ知れ 世の浮沈」 「シャクトリムシのように身を屈するのも、いずれは龍のように伸びるためだ。そのためには、奴隷になっても、下僕になっても構わない」 「苦労する身は厭わねど、苦労し甲斐のあるように」 「天地も人も皆気のみである。気を養えば、人間あとは行動に移すのみだ。 「人は旧を忘れざるが義の初め」 「生きるか死ぬかは時機に任せよう。世の人が何と言おうと、そんなことは問題ではないのだ」 「苦しいという言葉だけはどんなことがあっても言わないでおこうじゃないか」 「古くから天下のことを行う者は、大義を本分とし、決して他人に左右されることなく、断固として志を貫く。禍福や死生によって気持ちが揺れ動いたりするものではない」 「心すでに感ずれば、すなわち、口に発して声となる」 「直言実行、傍若無人、死を恐れない気迫があるからこそ、国のために深謀深慮の忠も尽くせるのだ」 「友人の信頼の度合いは人の死や緊急事態、困難の状況の時に分かる」 と、言っている高杉晋作、こんな粋な都々逸も残しています。 「三千世界の烏を殺し、主と朝寝がしてみたい」 |
| 突然の訃報哀しや秋の風 2017/10/10(火) |
 |
| 8日の朝、思い掛けない知人の訃報が入って来ました。 これには、一瞬、言葉を失くしました。 そして、人の世の無常を強く感じました。 その時、この思いをどう処理したらいいのかと思い惑いながら、 ネットをあれこれ検索していたら、まずは、次のような句や歌に 行きつきました。 秋風の吹き来る方に帰るなり 前田普羅 おしなべて物を思はぬ人にさへ心をつくる秋の初風 西行 更に、吉田兼好の『徒然草』第七段 あだし野の露きゆる時なく、鳥辺山の烟立ちさらでのみ住みはつるならひならば、いかにもののあはれもなからん。世はさだめなきこそいみじけれ。 あだし野の露が消える時なく、鳥辺山の煙がいつまでも上がり続けるように、人生が永遠に続くものならば、どうしてもののあはれなど、あるだろう。人生は限りがあるからこそ、よいのだ。 などという文章にも思いを馳せました。そして、この後、少し落ち着いて来てから、心に残る辞世の句を調べてみる気になりました。 散りぬべき 時知りてこそ 世の中の
花も花なれ 人も人なれ 心しらぬ 人は何とも 言はばいへ
身をも惜まじ 名をも惜まじ 風さそふ 花よりもなほ 我はまた
春の名残を いかにとやせん つひに行く 道とはかねて 聞きしかど
昨日今日とは 思はざりしを 石川や 浜の真砂は 尽くるとも
世に盗人の 種は尽くまじ 借り置きし 五つのものを 四つ返し
本来空に 今ぞもとづく 東路(あづまぢ)に 筆をのこして
旅の空 西のみくにの名所を見む あらうれし 行き先とほき 死出の旅 <大前田英五郎(侠客)> 君が為 尽くす心は 水の泡 消えにし後は
澄み渡る空 あはれなり 我が身の果てや 浅緑
つひには野辺の 霞と思へば 月も見て われはこの世を かしくかな <加賀千代 (俳人)> 人魂(ひとだま)で 行く気散(さん)じや 夏野原 <葛飾北斎> 手に結ぶ 水にやどれる 月影の
あるかなきかの 世にこそありけれ 世の中の 厄をのがれて もとのまま
帰るは雨と 土の人形 旅に病んで夢は枯野をかけ廻る <松尾芭蕉> 露と落ち 露と消えにし 我が身かな
浪速のことは 夢のまた夢 おもしろき こともなき世を おもしろく <高杉晋作> 浮世の月 見過しにけり 末二年(すえにねん) <井原西鶴> 裏を見せ 表を見せて 散る紅葉 <良寛> たらいから たらいにうつる ちんぷんかん <小林一茶> この世をば どりゃお暇(いとま)に
線香の 煙とともに 灰(はい) 人の死というものは、残酷なものです。でも、誰もが受け止めなければならないものです。今夜は、通夜に行くことにしています。 どんぐりのポトリと落ちて帰るかな 風天(渥美清) |
NEXT |
| GALLERY工+Withに戻る |